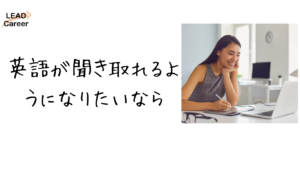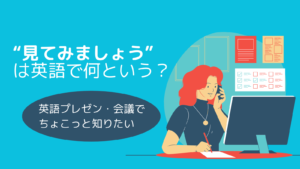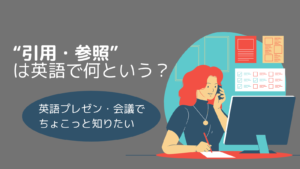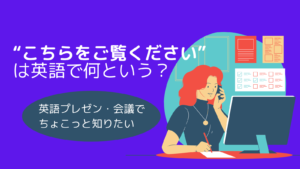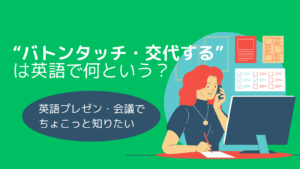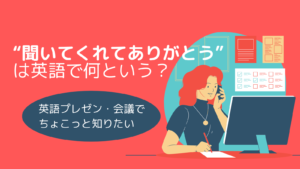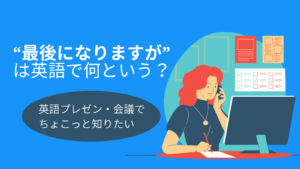2023年12月
Strategy to make your Japanese CV shine
Strategy to make your Japanese CV shine First of all, there are usually two types of CVs or Resume in Japan. T […]
英語が聞き取れるようになりたいと願う方の6つのヒントと教材とは
英語の聞き取り能力を向上させるためには、以下の対策を取ることが重要です。 これらのアプローチを組み合わせて実践することで、効果的な成果が期待できます。 リスニング教材の活用 英語のニュース、ポッドキャスト、オーディオブッ […]
英語プレゼンや会議で「見てみましょう」は英語で何という?注意点は?
プレゼンテーションや会議において、アイデアや情報を視覚的に伝えることは極めて効果的です。その際、「見てみましょう」に相当する英語表現を上手に活用することが重要です。このブログでは、英語プレゼンテーションや会議で「見てみま […]
英語プレゼンで「参照・引用」はどう表現する?注意点は?
英語プレゼンで「参照・引用」 プレゼンテーションやレポートにおいて、正確で信頼性のある情報を提供するためには、引用(citing sources)が欠かせません。特に英語プレゼンテーションでは、「出典」に相当する英語表現 […]
会議やプレゼンで「こちらをご覧ください」は英語で何という?注意点は?
プレゼンテーションや会議において、特定の情報や資料に聴衆の注意を引くことは不可欠です。「こちらをご覧ください」に相当する英語表現を使いこなすことは、情報の効果的な伝達につながります。このブログでは、「こちらをご覧ください […]
英語プレゼン・会議で「バトンタッチ・交代します」は英語で何という?注意点は?
プレゼンテーションや会議において、トピックやセクションの切り替えを円滑に行う(バトンタッチする、交代する)ことは、聴衆の理解を促進し、効果的なコミュニケーションを確立するうえで重要です。この表現がうまく使えないと、英語プ […]
「注目してください!」は英語プレゼンや会議で何という?注意点は?
プレゼンテーションや会議において、聴衆の注目を引くことは成功に不可欠です。そのために、効果的な英語表現を使用し、注意を集中させることが重要です。このブログでは、「注目してください」に相当する英語表現の使い方と、注意点につ […]
プレゼン最後に「聞いてくれてありがとう」は英語で何という?注意点は?
プレゼンテーションの締めくくりは、感謝の気持ちを表現することで印象を強化できます。「聞いてくれてありがとう」に相当する英語表現を使いこなすことは、聴衆とのつながりを深め、プロフェッショナリズムを示す重要な要素です。このブ […]
「次になりますが」「次は」は英語プレゼン・会議で何という?注意点は?
「次になりますが」は、会話や文章において次のトピックへの移行を示す際に使われます。 英語においても、同様の意味を持つフレーズを上手に使いこなすことは、スムーズなコミュニケーションに欠かせません。このブログでは、「次になり […]
英語プレゼン・会議で「最後になりますが」は何という?注意点は?
英語プレゼンで「最後になりますが」は、会話や文章の締めくくりに使われ、最後を締める重要な一言です。 私の経験からしても、「最後になりますが」といった際には、ぐっと、聴衆の注意が集まった感じがあり、この用語をどのように使う […]